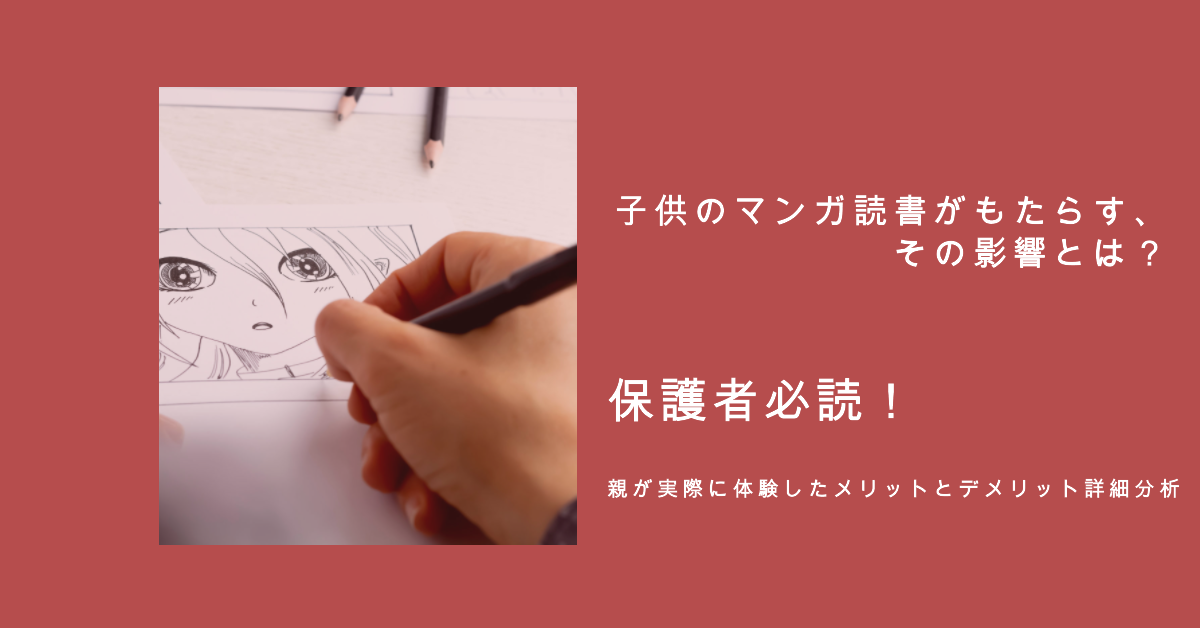
はじめに
こんにちわ。私は普通のサラリーマンで、小学生の子ども二人と妻と4人で暮らしています。
子どもがマンガを読むこと、良いと思いますか?悪いと思いますか?いろんな意見があると思いますが、我が家は子どもにマンガを読ませています。
最近ではマンガを読むことにメリットが多いことを言われることが多くなってきました。
しかし、読ませ続けたことで一概にメリットばかりとは言えないことに気が付きました。
この記事では、子どもがマンガを読むことのメリットとデメリットを我が家のリアルな体験談もあわせて紹介します。
読んでいただければ、我が家の経験が皆さんの子育ての参考になればと思います。
マンガが子どもに与える影響:メリット編
子どもの想像力の育成
マンガ読むことで一般的に言われているのはその視覚的な要素が強い特性から、子どもの想像力を促進すると一般的に言われています。
例えば、「ワンピース」のような冒険マンガは、子どもたちが異なる世界を想像し、創造力を育む上で重要な手助けを提供します。
我が家のリアルな体験談
息子たちが想像力を駆使していると感じた瞬間は、彼らが自分の部屋でダンボールの空き箱を使って工作を始めたときでした。
マンガの武器や防具を作って遊んでいる彼らを見て、その創造性に驚きました。彼らはダンボールを切ったり貼ったりして、様々な形状のものを作り上げていました。
ちなみに子どもたちは「NARUTO」の影響を強く受け、クナイや手裏剣などの武器を作っていました。
夏休みの工作の宿題では、「鬼滅の刃」に登場する刀を模したものをダンボールで作り、学校に持っていっていました。
これらの経験を通して、マンガが子どもたちの創造性や想像力にどれほど影響を与えているかを実感することができました。
読解力の向上
マンガが子どもの読解力を向上させると一般的に言われています。
読解力とは、文章やテキストを読む際に、そこに書かれている情報やメッセージを理解し、解釈する能力のことです。
この能力は単に言葉を読むだけでなく、文章の背後にある意味を把握し、それを自分の知識や経験と結びつけて考えるプロセスを含みます。
マンガの物語を追うことで、このような情報の理解と記憶が促進されます。
我が家のリアルな体験談
息子たちがマンガを通じて読解力を伸ばしていると感じた瞬間は、「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」を読んでいたときです。
この作品は相手に告白させるために頭脳戦を繰り広げる男女の恋愛を描いたもので、ギャグ要素も多く、息子たちは大笑いしながら読んでいました。
しかし彼らは物語のストーリーを理解するだけでなく、登場人物たちの心理状態や思考プロセスを推測することもできるようになりました。
それは彼らがテキストの深層を探り、言葉の背後にある意味を理解する力が成長している証拠です。
また、マンガの中で使用される難しい言葉や表現に対しても彼らは興味を持ち、自分で調べるようになりました。
これらの行動は、子どもたちが自主的に学ぶ態度を身につけていることを示しています。
新しい知識と情報を学ぶ
マンガを読むことで、子どもは新たな言葉や表現を学ぶことができるといわれています。
これは、彼らの語彙力を向上させるのにも役立ちます。
我が家のリアルな体験談
子どもたちは、マンガを読むことで、日常生活では使われないような新たな言葉や表現を学んでいます。
マンガの中で使用される難しい言葉や表現に対しても彼らは興味を持ち、自分で調べるようになりました。
これらの行動は、子どもたちが自主的に学ぶ態度を身につけていることを示しています。
人間関係の理解を深める力の成長
マンガは、様々な登場人物の心の動きを描き出し、読者に人間関係の理解を深める力を育む可能性があります。
子どもたちはこれらの物語を通じて、多様な立場や視点に触れる機会を得られます。
我が家のリアルな体験談
人間関係の理解を深める力については、マンガだけが原因ではないことは確かですが、子どもたちが理解するきっかけになっていると思います。
マンガがその理解を助ける一例として挙げると、「ドラえもん」はキャラクターが行動する理由やその結果となる反応が分かりやすく描かれているため、「このような行動をすれば友人に嫌がられる」といった事柄を子どもたち自身が理解するきっかけになると思います。
マンガが子どもに与える影響 デメリット編:
マンガの読書には多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。
デメリットについての我が家の対策については後述にまとめています。
悪い価値観の形成
一つは、暴力的な表現やグロテスクな描写、性的な表現による悪影響でると一般的に言われています。
たしかに、このような表現のある漫画を子どもに読ませるのは適切ではないと言えます。
我が家のリアルな体験談
マンガのギャグシーンでは、ツッコミとしての殴るシーンがしばしば描かれます。これは大袈裟な表現であり、子どもはそれを理解しにくいことがあります。
その結果、現実でも同様の行動を取ることがあり、これがやり過ぎになることがあります。
読書による運動不足
もう一つのデメリットは、子どもが長時間マンガを読むと身体活動が足りなくなり、健康面に問題を引き起こす可能性があると言われています。
我が家のリアルな体験談
マンガの影響かといわれるとどうかなと思うのですが、コロナの影響で、子供たちが外に出ることがなくなりました。
その時に時間があったので長時間マンガを読むことになりました。
コロナが比較的落ち着いたあとも一度出不精になってしまうとなかなか外にでなくなりました。
時間があればマンガを読むので、マンガの読書によりさらに外に出る機会を失わせたと実感した瞬間でした。
視力の問題
さらに、子どもが長時間マンガを読むと、目に負担がかかり、視力が低下する可能性があると言われています。
我が家のリアルな体験談
実際、我が家の息子たちは視力が下がり、眼鏡が必要になりました。
マンガだけが原因ではなく、遺伝的な要素やコロナの影響で外遊びが減り、スマホやテレビで動画を見る時間が増えたことも一因と考えられます。
しかし、眼科医からは、「長時間の読書は目に負担をかけるので、休憩を取るように」とのアドバイスを受けました。
これは、長時間のマンガ読書が視力の問題を引き起こす可能性があるというデメリットを実感した瞬間でした。
マンガによる現実逃避
最後に、マンガの世界があまりに魅力的すぎると、子どもは現実の問題から目を背けがちになります。
これは、現実の問題解決能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
我が家のリアルな体験談
6年生の息子が宿題を始める前に「宿題やる気がでない」や「ちょっと気分転換にマンガを読む」と言ってマンガを読み始めることがあります。
しかし、その「ちょっと」の時間が長引いてしまい、結果的に宿題を始めるのが遅くなってしまいます。
これは、マンガによる現実逃避の一例かと思います。
デメリットに対して我が家での対策
子どもたちがマンガを楽しむのはメリットも多く素晴らしいことですが、デメリットに対してが保護者が適切に対処する必要があると思います。
ここでは、マンガのデメリットに対して我が家でどのような対策を行っているかをご紹介します。
適切なマンガの選択
子どもにとって適切なマンガを選ぶことは非常に重要です。我が家では保護者の私が内容を確認しているマンガのみ自宅に置いています。
自分や妻が「面白いけど小学生にはちょっと…」と思うものは処分しました。
具体的なマンガタイトルを例にあげますと「闇金ウシジマくん」や「ジョジョの奇妙な冒険」などが我が家では当てはまりました。
これらは子供が中学生や高校生になり知能や心が成長してからだと考えています。
これは各ご家庭での個々の判断となると思います。
視力低下への対策
我が家では、タイマーを使って30分ごとに1-2分間、窓の外を見るようにしています。
これは目を休めるためです。
マンガだけではなく、テレビやパソコンの画面を見る時も、目には負担がかかるので同様にしています。
また、適切な照明の下で読むようにするように寝室では読書は禁止にしています。
リビングルームで適切な照明を準備し、環境を整えるようにしています。
現実逃避の防止
「現実逃避」とは、現実の問題から逃げるように、別のことに夢中になることです。
子どもたちがマンガに長時間浸かってしまうことがあります。
我が家では、マンガを読書に適度な制限を設け、子どもたちに他の活動や現実の問題にも目を向けることを教えています。
ただ、時間を区切りなさいと口で言っても聞くことはないので、マンガは自分の寝室に置くようにしています。
マンガをすぐとれる場所に置かないためです。
また、電子書籍でも読みますが、これはマンガを読みたい時に端末(ipad)を貸し出すようにしています。
親としてできること
マンガを教育ツールに!:マンガで子供の可能性を広げる方法
マンガから他の活動へシフトする
私は子供たちにマンガだけではなく、リアルでも色々な経験をしてほしいと考えています。
アウトドア活動とのバランスも重要で実際に体を動かし経験することは、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも良い影響を及ぼすと考えているからです。
なので、我が家ではマンガを利用しほかの活動に子どもの興味が向くようにしています。
我が家の場合での例をいくつかあげます。
例1:マンガ ➡ 小説(文字が主体の書籍)
我が家ではマンガだけでなく、小説などの文字が主体の書籍も子供たちに読んでほしいと思っていました。
そのため、「転生したらスライムだった件」のように、コミック版があるだけでなく児童書籍版も出版されている作品を選びました。
まずはコミック版を家に置いて子供たちの興味を引き、その後に小説版を購入。
これにより、今まであまり活字の書籍に触れていなかった子供たちも、自主的に小説に親しむようになりました。
この方法が良いスタートとなったことを実感しています。
例2:マンガ ➡ 野外活動
私たちは子供たちに、外の世界で様々な経験をさせたいと考えていました。
そのために、子供たちが興味を持ちそうなマンガを何冊か選び、読むことができるようにしました。
その中で子供たちに刺さったのが、同時期にアニメも放映されていた「ゆるキャン△」というマンガでした。
この作品はキャンプを主題としており、子供たちはキャンプへの興味を深め、夏休みには子供だけで参加できるサマーキャンプに行くことになりました。
よい経験になったと思います。
例3:マンガ ➡ スポーツ
私たちは子供たちに何か運動をしてほしいと考えていました。
そこで、スポーツをテーマにしたマンガをいくつか選び、子供たちが自由に読めるようにしました。
そして、その中でも特にささったのがこの『アオアシ』でした。
特に4年生の息子は、将来プロのサッカー選手になりたいと言い出し、今ではサッカークラブで毎日のように練習に励んでいます。
マンガを通じてコミュニケーションがとれる
マンガは親子のコミュニケーションツールとしても大変有効です。子どもが読んだマンガの内容について一緒に話すことで、子どもの考えや感情を深く理解する良い機会になります。
また、自分が子どもたちに言葉のニュアンスなどを言葉で教えるのが難しいとき、マンガのキャラクターを例に出すと、子どもたちもイメージをさせやすいです。
例えば、「いやみな言葉ってどんな感じ?」と聞かれたときなどは、「ドラえもん」にでてくるスネ夫がプールに誘ったのび太に対し、「わりいわりい。今年の夏はハワイですごすんだ。」っていう感じっていうとなんとなく伝わります。
子供に読ませて良かった!おすすめマンガとその理由
こちらにまとめましたので、興味があればぜひご覧ください。
まとめ
子どものマンガ読書は、適切に管理されると、子どもの成長にとって有益です。しかし、親としては、その影響を理解し、適切な対策を講じる必要があります。
子どもの読書行動を観察し、マンガと他の活動とのバランスを保ちながら、マンガを教育資源として活用する方法を探ることが重要です。
これが、保護者の皆様の参考になれば幸いです。
この記事では、親が実際に体験した子どものマンガ読書の影響について、メリットとデメリットを詳細に分析しました。
また、親としてどのように関与し、マンガを教育ツールとして活用するかについても考察しました。これが、保護者の皆様の参考になれば幸いです。